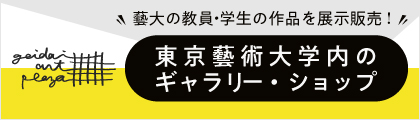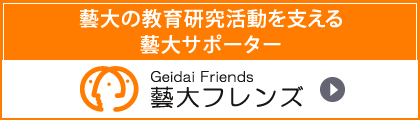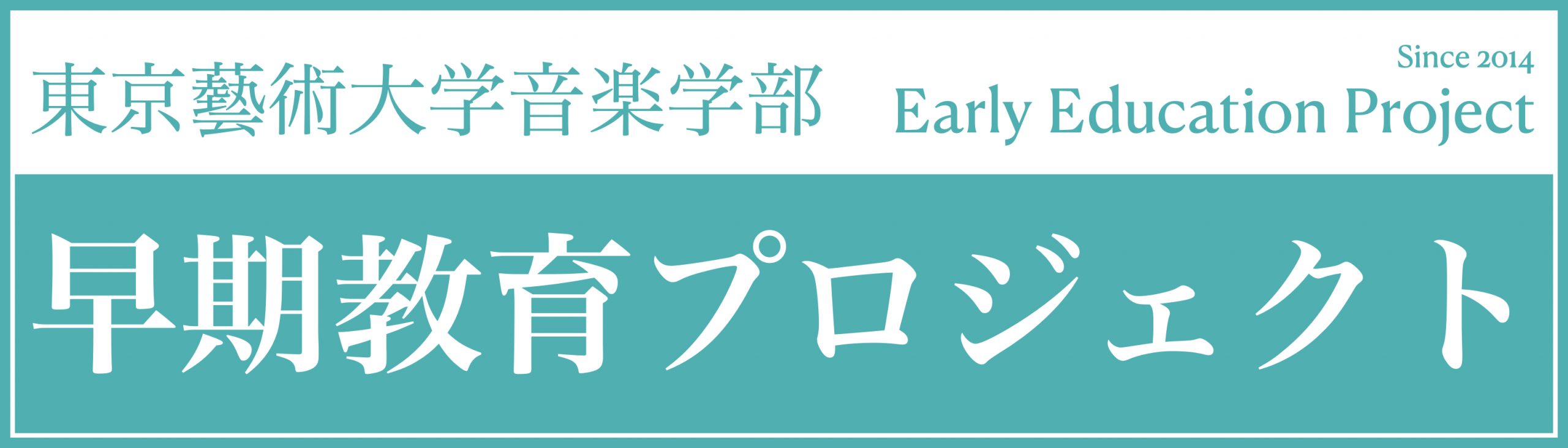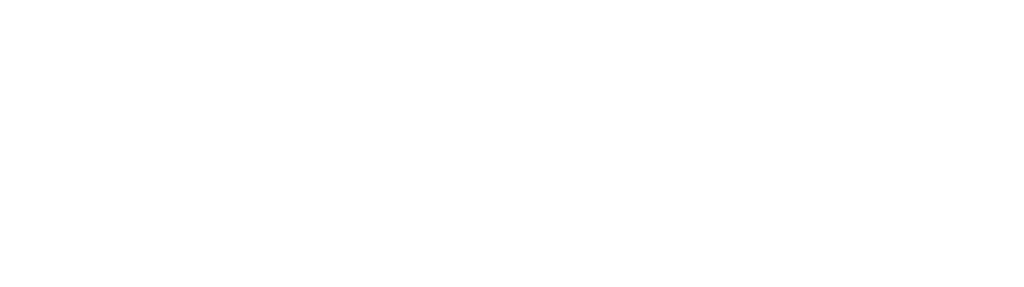- іу—ІЄ≈“™
- —І≤њ?—–Њњњ∆?Єљ фЩCйv?•ї•у•њ©`µ»
- ’є”Eїб?—Ё„аїб«йИу
- ОЏИу?іу—І«йИу
- —І…ъ…ъїо
- „дШI…ъ§ќЈљ§Ў
- “ї∞г?∆уШI§ќЈљ§Ў
- љћ¬ЪЖT§ќЈљ§Ў
- »л‘З«йИу
- ЋЗіу§ЋЉƒЄљ§т§є§л

µЏ∆я Ѓ∆яїЎ ∞≤≤њЅЉ°ЄЋЗіу„≈»ќ§ЋлH§Ј§∆°є
°°4‘¬§Ђ§й±Њ—Іљ®ЇBњ∆§ЋЊЌ»ќ§§§њ§Ј§ё§Ј§њ°£5‘¬§Ћ§ѕњ∆ƒЏ§«ЊЌ»ќ”Ыƒо•м•ѓ•Ѕ•г©`§т∆уї≠§Ј§∆§§§њ§ј§≠°ЄArt vs Architecture, Architecture with Art.°є§»§§§¶•∆©`•ё§«°ҐЋљ§ќљ®ЇBЉ“§»§Ј§∆§ќ±≥Њ∞§»їоД”§тљBљй§Ј§ё§Ј§њ°£
°°§≥§м§ё§«°Ґіу—І§ §…§ќ’–∆Є§«÷v—Ё§є§л§»§≠§ѕ°Єљ®ЇB§»§ѕЇќ§Ђ£њљ®ЇBЉ“§»§ѕЇќ’я§Ђ£њ°є§»§§§¶•∆©`•ё§«°Ґ∆љ§њ§ѓ—‘§®§–°Є„чЉ“§»§Ј§∆§…§ќ§и§¶§Ћ…ъ§≠§∆§≠§њ§Ђ£њ°є§»§§§¶‘Т§т§Ј§∆§≠§ё§Ј§њ°£Ћљ§ќИцЇѕ°Ґ•≥•ё©`•Ј•г•л§ Ћ ¬§Ђ§й§ѕ§«§≠§л§ј§±Њалx§т÷√§≠°Ґ Ћ ¬§ќ“јоm§тіэ§ƒ§ј§±§«§ѕ§ §ѓ°Ґ§и§кѕ»сlµƒ§ „ч∆Ј§т∞k±н§є§л§њ§б§ќЩCїб§тћљ§є§и§¶§Ћ§ §к§ё§Ј§њ°£љYєы°Ґ•№•й•у•∆•£•Ґ§д ÷џЌµ±§«§вШФ°©§ µЎ”т§Ћ≥ц§Ђ§±°Ґ•≥•я•е•Ћ•∆•£їо–‘§ќИц√槻§ §лТЗµг§≈§ѓ§к§тћб∞Є§є§л•є•њ•§•л§тЊA§±§∆§§§ё§є°£

ЊЌ»ќ”Ыƒо•м•ѓ•Ѕ•г©`£®2024ƒк5‘¬24»’£©§ќШФ„”
°°§љ§¶§Ј§њМgД’§тЌ®§Є°Ґ°Є…ъїо≠hЊ≥§тЅЉ§ѓ§«§≠§л§≥§»§є§ў§∆§ђ•«•ґ•§•у§ј°є§»ЋЉ§¶§и§¶§Ћ§ §к°ҐµЎ”т§ќ’nо}љвЫQ§ЋПꧮ§лљ®ЇB°Ґ§µ§й§Ћ§ѕљ®ЇB§ќ“‘«∞§д§љ§ќбб§ќ•„•н•ї•є§Ћ§вйv§п§лЩCїб§ђґа§ѓ§ §√§∆§§§ё§є°£љ®ЇB§ќ•∆©`•ё§ѕµЎ”т§ќ’nо}§ЋЇфПк§ЈЈщОЏ§ѓ°ҐЄяэh’я§д’ѕЇ¶’я§ќ…ъїо≠hЊ≥§ќЄƒ…∆°Ґњ’§≠Љ“§ќяm’эє№јн§»їо”√°Ґя^ѓEµЎ”т§ќ“∆„°іўяM§»•≥•я•е•Ћ•∆•£§≈§ѓ§к°ҐµЎ”тєћ”–Њ∞”Q§ќЊ@≥–°Ґ„”§…§в§ќя[§”§дљћ”э°Ґ…зїб∞ьУФ°ҐД”ќпЄ£мн°Ґ»Ћйg§»„‘»ї§ќ–¬§Ј§§йvВS§ §…§ §…°ҐґаᙧЋ§п§њ§к§ё§є°£
°°љсїЎ°Ґ§љ§у§ Ћљ§ќљ®ЇBїоД”§т°Є№њ–g§»§ќйv§п§к°є§»§§§¶°Ґ§§§ƒ§в§»§ѕя`§¶“յ㧫“К÷±§Ј§∆§я§њ§»§≥§н°Ґљ®ЇB§т÷Њ§є“‘«∞§ќ°Ґ10іъ§ќ§≥§н§ќ№њ–g§Ў§ќгњ§м§д°Ґљ®ЇB§т—І§” Љ§б§∆§Ђ§й§ќ№њ–g§Ў§ќЉµКБ°Ґ§љ§Ј§∆°Ґљ®ЇBЉ“§»§Ј§∆Пђњћ?љ}ї≠?“фШS?”≥ї≠?•’•°•√•Ј•з•у?ђFіъ√ј–g?•Ґ©`•»•„•н•Є•І•ѓ•»§ §…ШФ°©§ №њ–gоI”т§д№њ–gЉ“§њ§Ѕ§Ћі•∞k§µ§м°ҐЕfГP§Ј§ §ђ§й°Єљ®ЇB°є§тњЉ§®§∆§≠§њ§≥§»§тЋЉ§§Јµ§єЅЉ§§ЩCїб§»§ §к§ё§Ј§њ°£±Њ—І§Ћ„≈»ќ§Ј§∆§Ђ§й§»§§§¶§в§ќ°ҐЋљ§Ћ§»§√§∆§ќљ®ЇB§ѕ°Ґ§§§ƒ§в№њ–g§»є≤§Ћ§Ґ§√§њ§ќ§ј§»‘ў∞k“К§Ј§∆§§§ё§є°£
°°∆ж§Ј§ѓ§в»л—І љ§ќ—ІйL∞§ёў§Ћ§™§§§∆°Ґ±Њ—І§ђ°Є№њ–g§ђ…зїб§ЋЎХѕ„§«§≠§л§≥§»§т—–Њњ§Ј§∆МgЉщ§Ј§∆§§§ѓ°є»°§кљM§я§»§Ј§∆°Є№њ–gќіјі—–ЊњИц°є§тЅҐ§Ѕ…ѕ§≤§њ§≥§»§т÷™§к°Ґ§µ§й§Ћє»÷–µЎ”т§ќљїЅчТЗµг°ЄЋЗіу≤њќЁ°є§ќ’ыВд§Ћ§ѕ°Ґ∞≤≤њ—–Њњ “§»§Ј§∆§™ ÷Бї§§§є§лЩ