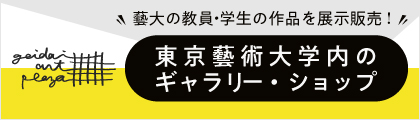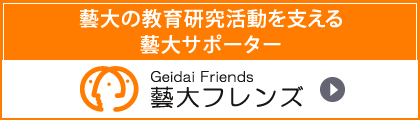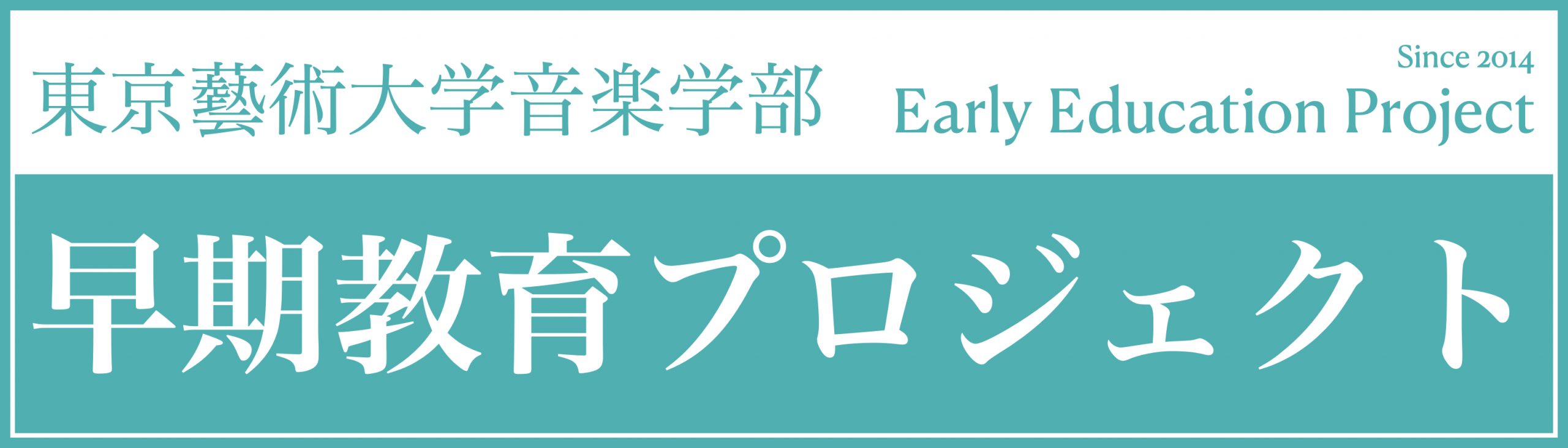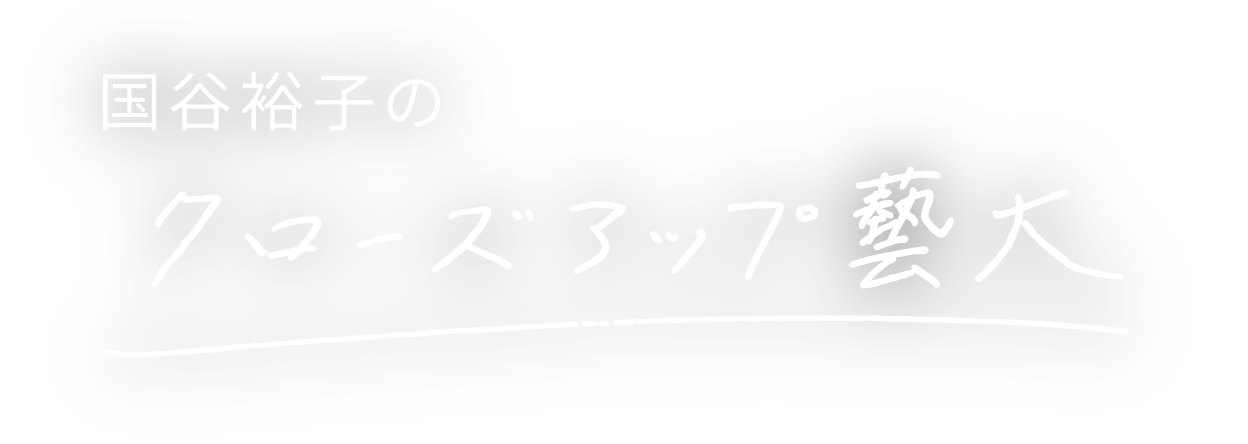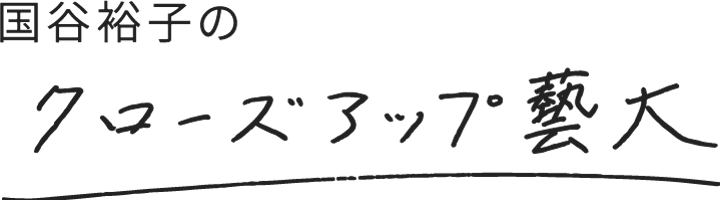- “óѧøÅŅŖ
- ѧ²æ?ŃŠ¾ææĘ?ø½ŹōCév?„»„ó„æ©`µČ
- Õ¹ÓE»į?ѯ׹»įĒéó
- Śó?“óѧĒéó
- ѧɜɜ»ī
- ×äIÉś¤Ī·½¤Ų
- Ņ»°ć?ĘóI¤Ī·½¤Ų
- ½ĢĀT¤Ī·½¤Ų
- ČėŌĒéó
- Ė“ó¤Ė¼Äø½¤ņ¤¹¤ė

µŚ¶žŹ®»Ų Ć«Ąū¼ĪŠ¢ “óѧŌŗ¹śėHÜæŠgŌģŃŠ¾ææĘ½ĢŹŚ£ÆĪ“Ą“Ōģ¾@³Š„»„ó„æ©`éL
„Æ„ķ©`„ŗ„¢„Ć„×Ė“ó¤Ē¤Ļ”¢¹ś¹ČŌ£×ÓĄķŹĀ¤Ė¤č¤ė½ĢŹŚ¤æ¤Į¤Ų¤Ī„¤„ó„æ„Ó„å©`¤ņĶؤø”¢Ė“ó¤ņ¤č¤źÉī¤Æ¾ņ¤źĻĀ¤²¤Ę¤¤¤¤Ž¤¹”£|¾©Ė“ó¤ĪĪØŅ»o¶ž¤ņÖŖ¤ź”¢ÕiÕߤȤȤā¤Ė”©¤Ė¤½¤ģ¤¾¤ģ¤ĖĖ¼¤¤¤ņŃ²¤é¤¹„ø„ć©`„Ź„ź„ŗ„ą”£²»¶ØĘŚ¤Ē¤Ŗ½ģ¤±¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
>> ß^Č„¤Ī”ø„Æ„ķ©`„ŗ„¢„Ć„×Ė“ó”¹
>> ”ø„Æ„ķ©`„ŗ„¢„Ć„×Ė“󔹤¬±¾¤Ė¤Ź¤ź¤Ž¤·¤æ
µŚ¶žŹ®»Ų¤Ļ”¢“óѧŌŗ¹śėHÜæŠgŌģŃŠ¾ææĘ½ĢŹŚ¤ĪĆ«Ąū¼ĪŠ¢ĻČÉś¤Ē¤¹”£éT¤ĻÉē»įѧ¤ä„Ż„Ō„å„é©`ŅōSŃŠ¾æ¤Ē”¢”ø„Æ„ź„Ø„¤„Ę„£„ō?„¢©`„«„¤„ō”¹¤ņÄæÖø¤¹Ī“Ą“Ōģ¾@³Š„»„ó„æ©`¤Ī„»„ó„æ©`éL¤āÕ¤į¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£2024Äź6ŌĀ”¢Ķ¬„»„ó„æ©`¤Īø½ŹōCév¤Ē¤¢¤ėŠ”ČŖĪÄ·ņÓÄīŁYĮĻŹŅ¤Ė¤Ę¤ŖŌ¤ņĖŤ¤¤Ž¤·¤æ”£
”¾¤Ļ¤ø¤į¤Ė”æ
Ć«ĄūĻČÉś¤¬„¤„ó„æ„Ó„å©`öĖł¤Ėßx¤Š¤ģ¤æŠ”ČŖĪÄ·ņÓÄīŁYĮĻŹŅ¤ĻŅōSѧ²æ¤Ī2ėA”¢¤¤¤Æ¤Ä¤ā¤Ī¾ĮŹŅ¤ņŗįÄæ¤ĖŅ¤Ź¤¬¤éi¤¤¤æĄČĻĀ¤Ī¤Ļ¤ŗ¤ģ”¢¤Ņ¤Ć¤½¤ź¤Č¤·¤æöĖł¤ĖėL¤ģ¤ė¤č¤¦¤Ė¤¢¤ź¤Ž¤·¤æ”£ÄæĮ¢¤æ¤Ź¤¤ČėæŚ¤ĒŃ„¤ņĶѤ¤¤Ē„¹„ź„ƄѤĖĀĤĢę¤ØČėŹŅ¤¹¤ė¤Č”¢¤½¤³¤Ė¤Ļ¹śÄŚĶā30Źż¤«¹ś¤«¤é¼Æ¤į¤é¤ģ¤æĆń×åSĘ÷¤¬K¤Ł¤é¤ģ”¢±¾¤äėjÕI”¢Š“Õę”¢S×V”¢åhŅō¤äÓ³ĻńŁYĮĻ”¢Ćń×åŅĀ×°¤Ź¤ÉŹĄ½ē¤Ī»½yÜæÄÜ”¢ĆńĖ×ŅōS¤Ė¤Ä¤¤¤ĘÖŖ¤ė¤³¤Č¤¬³öĄ“¤ėg¤ĖŲN¤«¤ŹæÕég¤¬¤¢¤ź¤Ž¤·¤æ”£””
Ć«ĄūĻČÉś¤ĻĆŲ¾³¤Čŗō¤Š¤ģ¤ėĖ“ó¤ĪÖŠ¤Ē¤ā¤³¤³¤Ļ”øĆŲ¾³¤ĪÖŠ¤ĪĆŲ¾³”¹¤Č±ķ¬F¤·¤Ę¤¤¤Ž¤·¤æ”£ŗĪ¹Ź”¢½ń”¢Ī“Ą“Ōģ¾@³Š„»„ó„æ©`éL¤ņÕ¤į¤ėĆ«ĄūĻČÉś¤Ļ¤³¤ĪöĖł¤Ė¹ā¤ņµ±¤Ę¤æ¤«¤Ć¤æ¤Ī¤«”£2rég¤Ė¼°¤ó¤Ą„¤„ó„æ„Ó„å©`¤Ļ”¢Š”ČŖŁYĮĻŹŅ¤Ī³Ö¤ÄŅāĮx¤«¤éŹ¼¤Ž¤ź”¢¬F“ś¤Ė¤Ŗ¤¤¤ĘÜæŠg¤Č¤ĻŗĪ¤«”¢Éē»į¤ĪÖŠ¤Ė¤Ŗ¤±¤ė„¢©`„ȤĪŅŪøī¤ä„¢©`„Ę„£„¹„ȤĪÉś¤·½¤Ė¤Ä¤¤¤Ę¤ā漤ؔ¢¤½¤·¤Ę¤³¤ģ¤«¤é¤Ī|¾©ĖŠg“óѧ¤Ī„ß„Ć„·„ē„ó¤Ė¤Ä¤¤¤Ę¤Ž¤Ē¤¤¤«¤±¤ė¤ā¤Ī¤Č¤Ź¤ź¤Ž¤·¤æ”£
„Æ„ź„Ø„¤„Ę„£„ō?„¢©`„«„¤„ō¤Č¤Ļ
Ć«Ąū
½ńČÕ¤ĪW¤Ī×ī“ó¤Ī„ß„Ć„·„ē„ó¤Ļ”¢¹ś¹ČĄķŹĀ¤ņ¤³¤³”¢*Š”ČŖĪÄ·ņÓÄīŁYĮĻŹŅ¤ĖßB¤ģ¤ĘĄ“¤ė¤³¤Č¤Ē¤·¤æ”£
¹ś¹Č
¤³¤Ī¤č¤¦¤ŹŁYĮĻŹŅ¤¬¤¢¤ė¤³¤Č¤ņu¤ŗ¤«¤·¤Ź¤¬¤éČ«¤ÆÖŖ¤ź¤Ž¤»¤ó¤Ē¤·¤æ”£
Ć«Ąū
Š”ČŖĻČÉś¤ĻW¤é¤ĪŹĄ“ś¤Ą¤Č„é„ø„Ŗ¤Č¤«„Ę„ģ„Ó¤Ė³öŃŻ¤µ¤ģ¤Ę¤¤¤æÓ”Ļ󤬤¤¤Ē¤¹¤Ķ”£¤³¤¦¤¤¤¦Ī÷ŃóŅōS¤ä„Ż„Ō„å„é©`ŅōSŅŌĶā¤ĪĆń×åŅōS¤ĪŹĄ½ē¤ĖÅdĪ¶¤ņ³Ö¤Ä·æŚ¤Ą¤Ć¤æ¤ČĖ¼¤¤¤Ž¤¹”£Ćń×åŅōSŅŌĶā¤Ē¤āä¤ļ¤Ć¤æŅōS¤ņ¤ä¤Ć¤Ę¤¤¤ėČĖ¤¬Ņ»»Ų¤ĻĶØ¤Ć¤æµĄ¤Č¤¤¤¦¤«”£
Š”ČŖŁYĮĻŹŅ¤Ļ¤ā¤Į¤ķ¤óŅōSѧ²æ¤ĒŅōSĆń×åѧ¤ņŃŠ¾æ¤·¤Ę¤¤¤ėČĖ¤ĖĄūÓƤ·¤Ę¤ā¤é¤Ø¤ģ¤Š¤¤¤¤¤ó¤Ē¤¹¤±¤É”¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Ī¤ņĆę°×¤¬¤ėČĖ¤Ļ¤½¤ģ¤Ą¤±¤Ē¤Ļ¤Ź¤¤Ż¤¬¤¹¤ė”£ĆĄŠgѧ²æ¤Īѧɜ¤Č¤«Ń§Ķā¤ĪČĖ¤ā”¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ā¤Ī¤Ė“„°k¤µ¤ģ¤Ę×Ō·Ö¤Ē×÷Ę·¤äĒś¤ņ×÷¤Ć¤æ¤ź”£
| *Š”ČŖĪÄ·ņÓÄīŁYĮĻŹŅ”ČÕ±¾¤Ė¤Ŗ¤±¤ėĆń×åŅōSѧ¤ĪŃŠ¾æÕߤȤ·¤Ę»īÜS¤·¤æ¹ŹŠ”ČŖĪÄ·ņŅōSѧ²æĒ°½ĢŹŚ£Ø1927-1983£©¤¬¹śÄŚĶā30Źż¤«¹ś¤Ē¤Ī„Õ„£©`„ė„É„ļ©`„ƤĒ §¼Æ¤·¤æåhŅōŁYĮĻ”¢Ó³ĻńŁYĮĻ”¢ķų”¢SĘ÷”¢Ćń×åŅĀ×°¤Ź¤É¤ņ±£¹Ü¤·”¢Ń§ÄŚĶā¤Ė¹«é_¤·¤Ę¤¤¤ė”£ |
¹ś¹Č
ŅĀ×°¤Č¤«Ó³Ļń¤Ė“„°k¤µ¤ģ¤ėČĖ¤ā¤¤¤ė¤Ē¤·¤ē¤¦¤Ķ”£Ūą±¾żŅ»¤µ¤ó¤āѧɜr“ś¤Ė“ó䄤„ó„¹„Ń„¤„¢¤µ¤ģ¤æ¤Č”¢×ņÄź¤ĪÕ¹Ź¾¤Ē½B½é¤µ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤·¤æ”£
Ć«Ąū
“óѧƥŠgš^¤Ē¤ĪÕ¹Ź¾£Ø2023Äź11ŌĀ10”«26ČÕ”øÜæŠgĪ“Ą“ŃŠ¾æöÕ¹”¹”¶„Æ„ź„Ø„¤„Ę„£„ō?„¢©`„«„¤„ō”·£©¤Ē¤Ļ”¢¤½¤¦¤¤¤¦½B½é¤ņ¤µ¤»¤Ę¤¤¤æ¤Ą¤¤Ž¤·¤æ”£Ūą±¾żŅ»¤µ¤ó¤“±¾ČĖ¤Ė¤č¤ė¤Č”¢ŅōSѧ²æ¤ĪŹŚI¤Ė¤Ļ¤Ū¤Č¤ó¤É³ö¤Ź¤«¤Ć¤æ¤±¤É”¢Š”ČŖĻČÉś¤ĪŹŚI¤Ą¤±¤Ļ³ö¤Ę¤¤¤Ę”¢¤¹¤“¤ÆAµ¹¤·¤Ę¤¤¤æ¤½¤¦¤Ē¤¹”£¶ą·Ö¤½¤ģ¤¬įį¤Ī„Ż„Ƅׄ¹¤Ī»īӤȤ«”¢„¤„Ø„ķ©`?„Ž„ø„Ć„Æ?„Ŗ©`„±„¹„Č„é¤Ė¤Ä¤Ź¤¬¤ė¤Ī¤«¤Ź¤Č”¢Ūą±¾¤µ¤ó¤ĪŅōS¤ņĀ¤¤¤Ę¤¤¤ė¤Č¤Į¤ē¤Ć¤Č¤ļ¤«¤ė¤Č¤³¤ķ¤¬¤¢¤ź¤Ž¤¹¤Ķ”£
Ė“ó¤Č¤¤¤¦¤ČĪ÷Ńó¤Ī„Æ„é„·„Ć„ÆŅōS¤Ī„¤„į©`„ø¤¬¤¤¤ó¤Ē¤¹¤¬”¢Š”ČŖĻČÉś¤ĻĪØŅ»o±Č¤Č¤¤¤¦¤«”¢”øŹĄ½ēŅōS”¹¤Č¤Ē¤āŗō¤Ö¤Ł¤ŅōS¤ĪĻČńlÕߤĄ¤Ć¤æ”£
 1971Äź „¢„Õ„ź„«Õ{Ėr¤ĪŠ”ČŖĪÄ·ņ£ØÓŅ£©£ØŠ”ČŖĪÄ·ņÓÄīŁYĮĻŹŅĖłŹi£©
1971Äź „¢„Õ„ź„«Õ{Ėr¤ĪŠ”ČŖĪÄ·ņ£ØÓŅ£©£ØŠ”ČŖĪÄ·ņÓÄīŁYĮĻŹŅĖłŹi£©
¹ś¹Č
¤Č¤Ę¤ā„·„ó„Ü„ź„Ć„Æ¤ŹøŠ¤ø¤¬¤·¤Ž¤¹”£½ń¤Ļ„Ą„¤„Š©`„·„Ę„£”¢¶ąŠŌ¤¬ÖŲŅ¤µ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹¤«¤é”£
Ć«Ąū
Š”ČŖĻČÉś¤ĻĖ“ó¤Īs“ś½ĢT¤ĪÖŠ¤Ē¤ā„¹„æ©`¤Ī1ČĖ¤Ē¤¹¤¬”¢Ė“ó¤ĪŅōSѧ²æ¤ĻĪ÷ŃóŅōSÖŠŠÄ¤Ą¤Ć¤æ¤Č¤¤¤¦¤³¤Č¤ā¤¢¤Ć¤Ę”¢²ŠÄī¤Ź¤¬¤é×ī½ü¤ĻĶü¤ģ¤é¤ģ¤Ę¤¤¤ėøŠ¤ø¤¬¤·¤Ž¤¹”£ÕZ¤źæŚ¤¬¤¹¤“¤ÆÉĻŹÖ¤Ē”¢¤ŖŌ¤āĆę°×¤«¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹¤č”£
2022Äź¤ĖŠĀŌO¤µ¤ģ¤æĪ“Ą“Ōģ¾@³Š„»„ó„æ©`¤Ē¤Ļ”¢¤³¤¦¤¤¤¦Ćń×åSĘ÷¤Ī±£“ę¤äŠŽĶ¤Č¤«¤āŃŠ¾æ¤Ī„Ę©`„Ž¤Ė¤·¤æ¤¤¤ČŌ¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£Ąż¤Ø¤ŠČżĪ¶¾¤Ņ¤Č¤Ä¤Č¤Ć¤Ę¤ā”¢ĆؤĪʤ¤Č¤¤¤¦ĖŲ²Ä¤¬Ź¹¤Ø¤Ź¤Æ¤Ź¤Ć¤Ę¤¤¤ė¤Ī¤Ļ¤č¤ÆÖŖ¤é¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹¤¬”¢»½ySĘ÷¤ĻĀČĖ¤āp¤Ć¤Ę¤¤¤Ę”¢¤Ž¤µ¤Ė¾@³Š¤¬Ī£¤Ö¤Ž¤ģ¤Ę¤¤¤ė”£SĘ÷¤ņ¤É¤¦×÷¤ė¤Č¤«”¢SĘ÷¤ņ×÷¤ėĀČĖ¤äµĄ¾ß¤ņ×÷¤ėĀČĖ¤ņ¤É¤¦½Mæ»Æ¤¹¤ė¤«¤Č¤«”¢¤½¤¦¤·¤æ„¤„ó„Õ„é¤Ī¤³¤Č¤ĻĖ“ó¤Ī¤č¤¦¤Ź“óѧ¤¬æ¼¤Ø¤ėrĘŚ¤ĖĄ“¤Ę¤¤¤ė¤ČĖ¼¤Ć¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤Č¤ņŃŌ¤¤Ź¼¤į¤ė¤Č”¢ŗĪ¤ā¤«¤ā¤ä¤é¤Ź¤¤ć¤¤¤±¤Ź¤¤¤Č¤¤¤¦Ō¤Ė¤Ź¤ź¤Ž¤¹¤¬”£
¹ś¹Č
Ī“Ą“Ōģ¾@³Š„»„ó„æ©`¤ĻŗĪ¤ņÄæÖø¤·¤Ę¤¤¤ė¤Ī¤Ē¤·¤ē¤¦¤«”£
Ć«Ąū
ŌŖ”©¤Ļ„¢©`„«„¤„ō„»„ó„æ©`µÄ¤ŹĪ»ÖĆø¶¤±¤«¤éŹ¼¤Ž¤Ć¤æ¤ó¤Ą¤ČĖ¼¤¤¤Ž¤¹”£Ē°ČĪ¤Ī„»„ó„æ©`éL¤ĪĶ©Ņ°ĪÄĮ¼ĻČÉś¤ĻĆĄŠgѧ²æ¤ĪĪÄ»ÆŲ±£“ęѧ¤ĪĻČÉś¤Ē¤¹¤Ķ”£¤±¤ģ¤É¤ā”¢„¢©`„«„¤„ō„»„ó„æ©`¤Č¤¤¤¦¤Č¤É¤¦¤·¤Ę¤ā¹Å¤¤¤ā¤Ī¤ņ¼Æ¤į¤æ¤Ą¤±¤ĪŁYĮĻŹŅ¤ČĖ¼¤ļ¤ģ¤¬¤Į¤Ē¤¹”£¤½¤¦¤Ē¤Ļ¤Ź¤Æ¤Ę”¢¤ą¤·¤ķ¤½¤ģ¤ņ»īÓƤ·¤Ę”¢½«Ą“¤ĪĖ“ó¤ņ¤Ä¤Æ¤ėŁYŌ“¤Ė¤·¤Ę¤¤¤¤æ¤¤”£¤½¤¦¤·¤æĪ“Ą“Ö¾Ļņ¤Ē½ĢÓż¤Ź¤źĶā²æ¤Ų¤Ī°kŠÅ¤Ė¤Ä¤¤¤Ę漤ؤė¤æ¤į¤Ė”¢”°„¢©`„«„¤„ō”±¤Č¤¤¤¦ŃŌČ~¤ņ¤¢¤Ø¤ĘŹ¹¤ļ¤ŗ¤Ė”øĪ“Ą“Ōģ¾@³Š„»„ó„æ©`”¹¤Č¤¤¤¦Ćū³Ę¤Ė¤·¤æ¤Ī¤Ą¤ČĖ¼¤¤¤Ž¤¹”£
Ė“ó¤Ė¤Ļ¤¤¤ķ¤¤¤ķ¤ŹŁYŌ“¤¬¤¢¤Ć¤Ę”¢¶ą¤Æ¤ĻĆĄŠgš^¤Č¤«ķųš^¤Č¤«¤Ė¤¢¤ė¤ó¤Ē¤¹¤¬”¢Ąż¤Ø¤Š¤³¤¦¤¤¤¦Š”ČŖŁYĮĻŹŅ¤ß¤æ¤¤¤Ź”¢ķųš^¤Ē¤āĆĄŠgš^¤Ē¤ā¤Ź¤¤¤ā¤Ī¤¬¤æ¤Æ¤µ¤ó¤¢¤ė”£¤½¤¦¤¤¤¦¤ā¤Ī¤ņ¤ā¤¦ÉŁ¤·¤Ž¤Č¤į¤æŠĪ¤ĒæÉŅ»Æ¤·¤Ę”¢·eOµÄ¤ĖŹ¹¤Ć¤ĘĶ